梅雨になると、なんとなく体がだるくて、やる気が出ない……。 そんな「つゆダル」や「湿気負け体質」に悩んでいる方に向けて、 今回は東洋医学の視点から、体質サポートの考え方をご紹介します。
「運動してもスッキリしない」「食欲もなくて体が重い」……。 そんなときは、体の内側から整えるアプローチも役立つことがあります。
🌿 梅雨の不調対策に用いられる代表的な漢方処方
※以下は、一般的に知られている特徴であり、使用にあたっては必ず医師や薬剤師にご相談ください。
【五苓散(ごれいさん)】
- 特徴:体内の余分な水分の巡りを整えるとされ、むくみ・頭重感・めまい・吐き気などの不調がある方に用いられることがある処方。
- 傾向:水分代謝が乱れやすく、トイレが近い、頭が重いと感じやすい人に。
【六君子湯(りっくんしとう)】
- 特徴:胃腸の働きを整え、食欲不振や胃もたれに用いられることがある。
- 傾向:胃腸が弱く、ストレスや季節の変化で不調を感じやすいタイプに。
【香蘇散(こうそさん)】
- 特徴:気の巡りをサポートし、気分の落ち込みや緊張による体調不良に対処する目的で使われることがある。
- 傾向:梅雨どきになると、気分の重さやイライラが出やすい方に。
【補中益気湯(ほちゅうえっきとう)】
- 特徴:体力の低下や慢性的なだるさに使われることがあり、全体的な元気不足を補うとされる。
- 筆者の体験:更年期のような慢性的なだるさに悩まされていた頃、婦人科で処方され、継続的に服用することで徐々に体が軽く感じられるようになりました。個人的にはとても助けられた経験があります。
【苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)】
- 特徴:上半身の水分バランスを整える目的で、めまいやふらつきがある場合に用いられることがある処方。
【防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)】
- 特徴:下半身の水分代謝を促し、むくみや関節の違和感に用いられることがある。
- 筆者の体験:利尿作用は実感できましたが、全体的なだるさへの大きな変化は感じにくく、私にはあまり合わなかったように思います。
🧘♀️ 漢方を選ぶときの注意点
漢方薬は「誰にでも効く」ものではありません。 体質や不調の傾向に応じた処方を選ぶ必要があるため、自己判断せず専門家に相談するのが安心です。
また、漢方薬は症状を一時的に抑えるのではなく、体全体のバランスを整えることを目的としているため、 日々の食事・睡眠・生活習慣の見直しと組み合わせることが大切です。
☔「つゆダル」体験記事もチェック!
👉 梅雨だる?それ、私のことですけど?~運動したらびっくりするほど気分爽快だった話~
筆者自身の体験をもとに、湿気による不調や体のだるさにどう向き合ったかをご紹介。 「つゆダルかも?」と思った方に読んでほしい記事です。
📝 免責事項
本記事は筆者の体験と一般的な情報をもとに、梅雨の不調に関する東洋医学的な視点を紹介する内容です。掲載している漢方薬の処方例や効果については、あくまで一例であり、すべての方に当てはまるわけではありません。
記載内容は医療行為や診断・治療を目的としたものではなく、参考情報としてご利用ください。実際の服用にあたっては、必ず医師や薬剤師など専門家にご相談のうえ、ご自身の体調や症状に合わせてご判断ください。
本記事の情報に基づいて生じた損害やトラブル等については、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いかねます。詳しくは当サイトの免責事項ページをご参照ください。

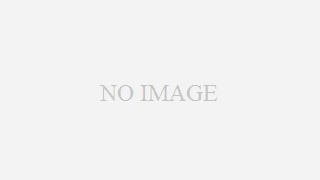
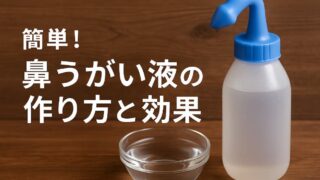

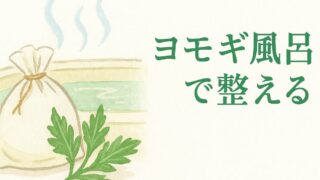



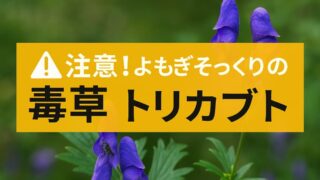
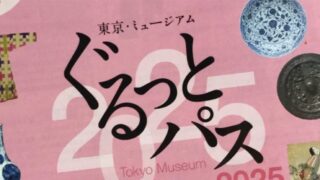





コメント