近年、夏の暑さが年々厳しくなり、熱中症への対策がますます重要になっています。そんな中、みなさんも耳にすることが増えた**「熱中症警戒アラート」**。この制度はいつから始まり、なぜ導入されたのでしょうか。
熱中症警戒アラートとは?
熱中症警戒アラートは、熱中症の重大なリスクが予測される日に、環境省と気象庁が共同で発表する注意喚起の制度です。国民に対して、外出や運動を控えるなど、熱中症への厳重な警戒を促します。
発令基準は、暑さの厳しさを示す**「WBGT(暑さ指数)」**が一定値を超えることです。WBGTは、気温だけでなく湿度や日射、風速なども総合的に評価するため、より体感に近い暑さを表す指標として使われています。
いつから始まった?導入の歴史
- 2020年夏:関東甲信地方で先行して試行導入されました。
- 2021年4月:試行導入での成果を踏まえ、全国での本格運用が始まりました。
なぜ導入されたのか?
熱中症警戒アラートが導入された背景には、近年の熱中症による死亡者数や救急搬送件数の増加があります。従来の「注意喚起」だけでは、多くの人々に危険性を十分に伝えきれていないと判断されたためです。
特に、日中の厳しい暑さに加え、湿度や夜間の気温の高さが重なることで、高齢者や子どもを中心に重症化のリスクが高まっていました。
導入のきっかけとなった「2018年の猛暑」
この制度が導入される直接的なきっかけとなったのは、2018年の記録的な猛暑です。この夏は「災害級の暑さ」と称され、観測史上初めて東京都内で気温が40℃を超えるなど、全国で多数の熱中症による救急搬送や死亡事例が報告されました。
この事態を受け、政府はより強力で分かりやすい警報の仕組みが必要であると判断。翌年から制度設計が進められ、現在の熱中症警戒アラートへとつながりました。
アラートが発令されたらどうする?
アラートが発令されると、テレビやラジオ、SNSなどを通じて周知されます。学校や職場、地域社会では、屋外での運動を原則中止したり、不要不急の外出を控えるなど、具体的な熱中症対策が推奨されます。
このアラートを一つの目安として、より一層の熱中症予防を心がけることが大切です。

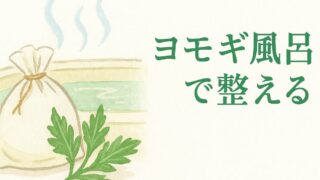


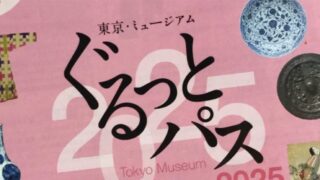




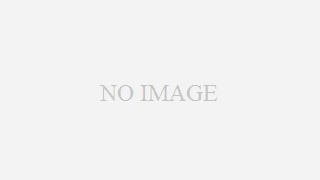
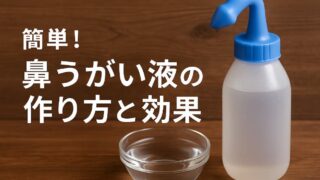
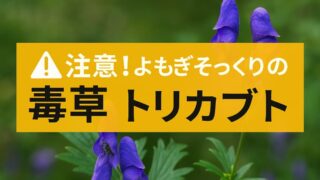
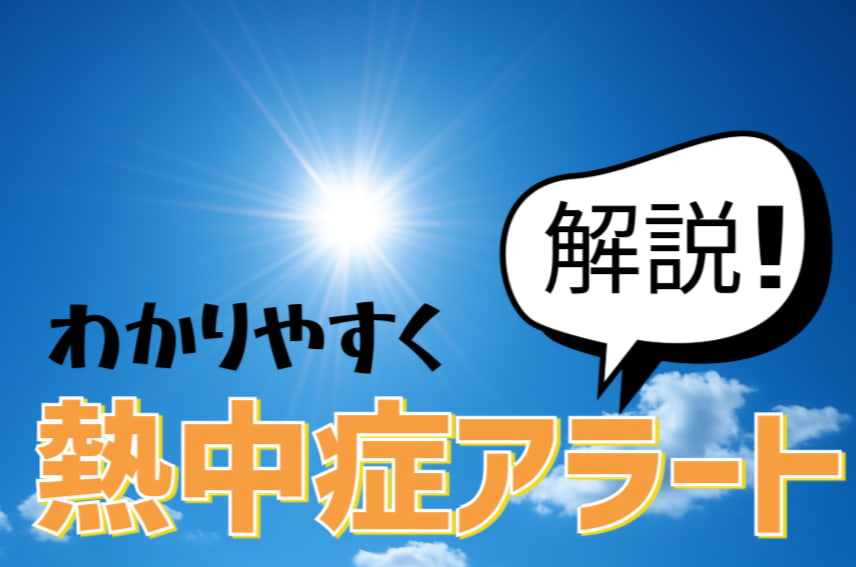
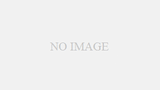

コメント