「あなたの親は本当に大丈夫ですか?」
そう聞くと、多くの方が「うちの親はしっかりしているから大丈夫」と答えます。
ですが、介護士として長年高齢者と接してきた経験から、私はこう言い切ります。
とくに離れて暮らしている場合、
子どもが思っているより、親の認知機能は確実に衰えています。
そして子どもの前では、別人のようにしっかり振る舞うのです。このため、介護士や医療者と家族の間で”認識のずれ”が生じることも少なくありません。
「早めに対応を」と思っても、なかなか前に進めないのです。
しかし、それは“親心”。
「心配をかけたくない」「迷惑をかけたくない」という思いから、懸命に頑張っているのです。
そんな子どもへの愛情から弱みや不安を隠します。
結果として、認知症や判断力の低下に気づくのが遅れ、詐欺や事故に巻き込まれるリスクが高くなります。
最近多発している「県警」や「捜査二課」を名乗る詐欺電話
近年増えているのが、警察を装う劇場型詐欺です。
「あなたの口座が事件に使われた」
「捜査のため、口座情報やキャッシュカードが必要」
といった内容で、複数人が役割を演じ、電話で物語を作り上げます。
「警察からの電話」=「信じていいもの」という意識が強い高齢者ほど、
警戒心が解けやすく、被害に遭いやすいのです。
高齢者が引っかかりやすい理由
- 権威に弱い:「警察」「役所」「銀行」といった肩書きに安心する
- 焦らされると言葉に従ってしまう:「至急」「今日中」などのフレーズに弱い
- 一人暮らしで孤立:久々の電話でつい長話してしまう(電話が嬉しい)
- 加齢による情報処理の遅れ:疑うより先に信じてしまう
- 子どもの前では元気に振る舞う:衰えを隠すため、家族は気づきにくい
家族の心理が“気づき”を遅らせる
介護士が「あれ?」と違和感を持ち、すぐご家族に伝えても、
「うちの親はそんなはずない。まだ大丈夫。」と
受け入れられないことは少なくありません。
「親には元気でいてほしい」
「衰えていく姿を見たくない」
そんな深層心理が働くからです。
しかし、第三者の指摘を素直に受け入れ、早めに認知症検査をすることは大きな予防策。
詐欺に遭ったり、徘徊で行方不明になってからでは遅いのです。
私自身、実際に行方不明で大騒ぎになった現場を経験しました。
その時のご家族の後悔は、言葉では言い表せません。
第三者から聞く親御さんの様子こそ、あなたがいないときの“本当の姿”です。
これを心に刻んでください。
今すぐできる詐欺防止の具体策
1. 電話設定を見直す(最優先)
※機種によって名称や設定が異なるため、取扱説明書やメーカーサイト・ショップで確認
- スマホの場合
- iPhone → 「設定」→「電話」→「不明な発信者を消音」ON
- Android → 電話アプリ設定→「迷惑電話ブロック」や「不明な番号を拒否」ON
- ガラケー(フィーチャーフォン)の場合
多くの機種で「電話帳登録外着信拒否」機能があります。
メニュー → 設定 → 着信制限/セキュリティ → 「電話帳登録外拒否」ON - 固定電話の場合
ナンバーディスプレイ対応機種で「登録外着信拒否」を設定
家族が設定を行い、「大事な人は全部登録してあるから安心して」と説明してあげるのがポイントです。
2. 固定電話に”自動通話録音機”を設置する
自動通話録音機とは、詐欺や迷惑電話を未然に防ぐための、警告・録音機能を搭載した機器です。
電話を受信すると「この通話は録音されます」という音声が流れ、警告します。
詐欺犯は録音されること嫌がるので、多くの場合はすぐに電話を切ります。
3. 留守番電話を活用する
留守番電話を活用することで、不審な電話に直接対応する必要がなくなります。
知らない番号からの電話にはすぐに出ず、留守番電話にメッセージを残させましょう。
詐欺師はメッセージを残すことを避ける傾向があるため、この方法も非常に有効です。
4. 合言葉を決める
「本当に家族からの連絡なら、この言葉を使う」という暗号を事前に決めておく。
5. 詐欺の話題を日常的に出す
地域ニュースや実例を共有し、情報を“今のこと”として意識づける。
まとめ
- 高齢の親は、子どもの前では元気に見せかけることがある
- 認知機能の衰えは、家族よりも先に“他人”に見抜かれることがある
- 気づいたときには、すでに詐欺や事故が起きていることも少なくない
- 物理的な電話ブロック設定+日常的な声かけが最大の防御
「うちの親は大丈夫」という油断こそ、詐欺犯にとって最高の隙。
今すぐできる設定と、家族の関わりで、大切な人を守りましょう。
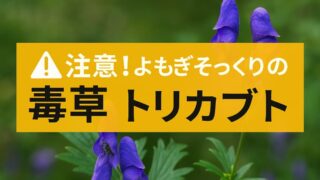


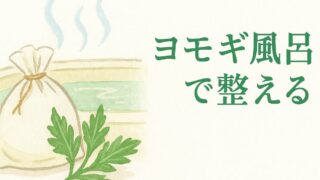

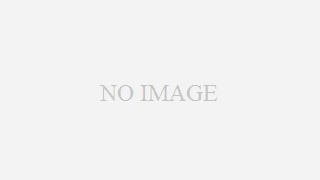

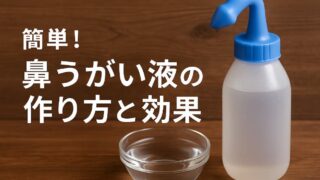


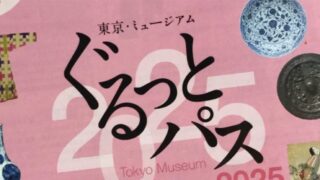





コメント