元介護士が語る、徘徊・行方不明の現実と防ぐためにできること
警察庁の発表によると、2024年に認知症やその疑いにより行方不明になった人は1万8121人、このうち還らぬ人となったのは419人です。
大切な人が、ある日突然、目の前からいなくなる。
そんな悪夢が、あなたの身にも起こるかもしれません。
「昨日まで普通に過ごしていたのに、急に帰ってこない」
徘徊による行方不明は、家族にとって悪夢のような出来事です。
しかし実際には、その危機は突然ではなく、じわじわと忍び寄っていたサインを見逃していたケースが多くあります。
その背景には、子どもが現実を受け入れられず、早期の対策が後回しになってしまう現状があります。
認知機能や判断力の低下を早めに察知することが、こうした事態を防ぐ第一歩です。
→ 離れて暮らす親の認知機能を確認する方法
私の体験から「1人暮らし・女性(80)Fさんの話」
ある冬の夜、自宅でくつろいでいると、夜10時過ぎにFさんの息子さんから慌てた電話が入りました。
「母が見守りカメラに映らない!」
急いで駆けつけると、玄関のドアは開け放たれ、室内はもぬけの殻。
家族に警察への捜索願を出すよう促し、私もすぐに捜索に出ました。
普段のケアでよく一緒に行っていたスーパーや病院周辺を手がかりに探しましたが、見つからない。
その日は真冬で冷え込みが厳しく、Fさんは上着を持たずに出て行った形跡がありました。
その後の展開
約2時間後、警察から連絡が入りました。
Fさんは大きな国道の真ん中を、下着一枚で歩いているところを通行人に発見され、通報されて保護されていたのです。
発見場所は、自宅からなんと約4キロも離れていました。
幸い、自宅周辺が人通りの多い地域で、しかも目立つ場所を歩いていたため通報につながり、徘徊の時間も比較的短く、大事には至りませんでした。
見守りカメラを設置していたことも、異変に早く気付く重要なきっかけとなりました。
しかしもし、人けのない夜道や川沿い、山道に入っていたら――発見は大幅に遅れ、命に関わる事態になっていたかもしれません。
認知機能の低下ーーなぜ発見が遅れるのか?
- 「まだ大丈夫」という思い込み
変化を指摘されても「そんなはずはない」と否定してしまう心理が働く。 - 生活のサインを見逃す
冷蔵庫の中身、服装、薬、部屋の状態などの小さな変化を軽視してしまう。 - 早期対策の先送り
見守りカメラやGPS、鍵の管理など、必要な対策を後回しにしてしまう。
防ぐためにできること
- 日常的なサインを観察する
→ 認知機能低下を見抜く6つのサイン - 玄関や窓に補助錠を設置する
- 見守りカメラやGPS端末を活用する
- 徘徊SOSネットワークに登録する(地域包括支援センターで受付)
- 近所の人と情報共有しておく
まとめ
徘徊や行方不明は「突然」起きるように見えて、実は小さな兆候が積み重なった結果です。
家族がその現実を受け入れ、早めに対策をとることが、命を守る最も確実な方法です。
「まだ大丈夫」という油断が、最悪の事態を招くこともあります。
今日からできる観察と環境づくりで、大切な人を守りましょう。

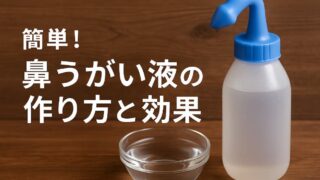
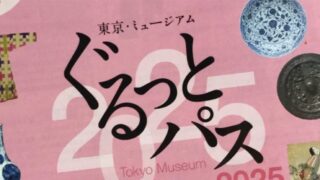

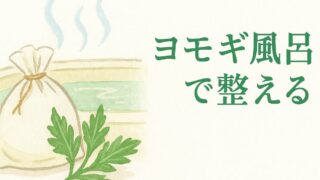




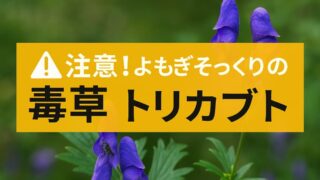

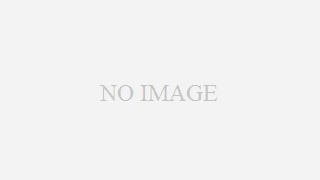
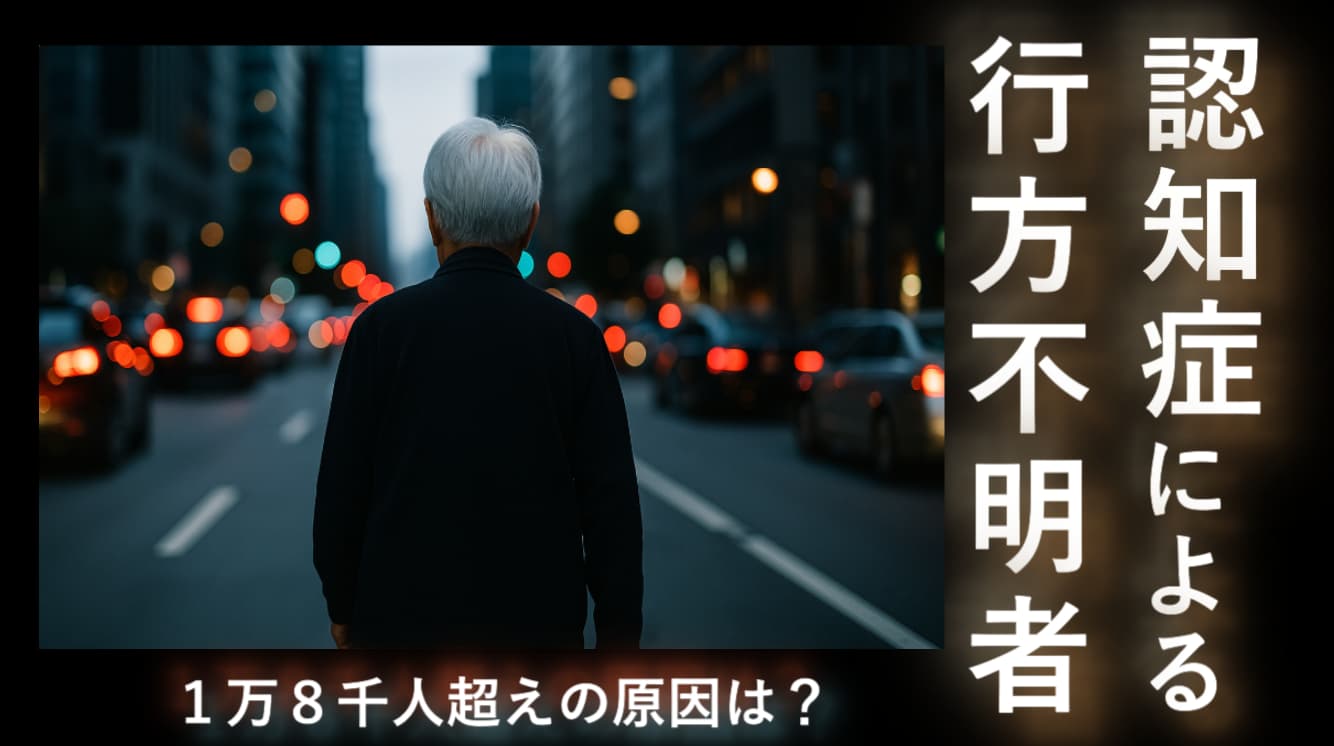




コメント